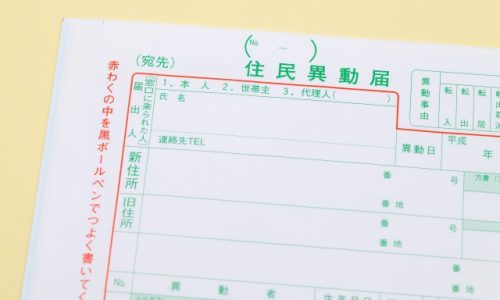今まで付き添ってきた夫が、この世を去らざるを得なくなりました。残された妻子は旦那さんからの遺産を託されることになります。しかし、どうやって分けていくかが問題となります。
■夫のものは妻子のもの
残された財産は遺産として扱われます。それは誰に帰属するかというと夫ではなく残された妻子となります。遺産分割の順位に基づくと、以下の通りになります。
①第一順位→妻や子供
法定相続分→それぞれ1/2とする
②第二順位→亡き夫の両親
法定相続分→配偶者が2/3、両親は1/3
③第三順位→兄弟姉妹
法定相続分→配偶者が3/4、兄弟姉妹は¼
遺言状がない場合のケースですが、実際の家族構成はかなり複雑となっていますので、考えただけでも非常に厄介となっています。遺産相続におけるトラブルの火種にもなっていることから、色んな意味でも難しい話です。財産分与くらいはトラブルなくスムーズに進めておきたいものです。
■旦那さんが生前書いた・・・
遺言状についてお話します。夫が生前、財産分与などについての取り決めを遺言状に託しておくことになります。しかし、それは一定の方式があるというのが法律で定められており、死後から効力を発揮します。
遺言状は以下のことができます。しかし、遺産の話について関係があるもののみ紹介します。
①財産の処分
残された財産は、遺産として残されます。それは残された妻子に託さなければならないのは前述の通りです。しかし、相続人以外の方に託したり財団を創立する際に使いなさい、というときに効力があります。
②相続分指定と委託
財産配分については、法律で定められています。しかし、被相続人の意向がありますので、それに従って配分を見直したりすることができます。
③分割方法指定と委託
遺産相続となると、その配分についてのトラブルが起こりやすいのは前述の通りです。しかし、被相続人から見ればいい迷惑です。そのようなトラブルをなくすため、分配方法そのものを見直すことができます。
④分割禁止
分割方法指定と委託の続きになりますが、分割については一定期間禁止(つまり、一定の猶予期間を与える)をすることにより、ノンストレスで公平に遺産分割ができるようにすることです。ただし、5年以内に解決しなければなりません。
◎遺産の種類
2種類が存在します。
①自筆証書遺言
基本的には自分で書くことになります。紙とペンさえあれば成立しますがパソコンを使っての作成は無効とされます。しかし、発見されたら家庭裁判所へ提出しなければならず、裁判官から検認を受けなければ開封することができません。なお、検認については数年後に撤廃されます。
②公正証書遺言
公証役場の公証人との合同作業となり、被相続人から聞いた話を遺言状として落とし込んでいきます。専門家の確認作業こそ入りますが、効果が無効になるリスクが少なくて済みます。自筆証書遺言と比べればの話ですが・・・。デメリットは自筆と比べ費用がかかることです。
◎遺留分
「この財産は、妻にすべてを託す」といった遺言内容だったらどうなるのでしょうか?子供からすれば「自分にはもらえないのか? おかしいだろ」となりますよね。しかし、相続人には一定の額を得ることが法律で保障されています。
遺留分減殺請求の行使により、相手方と話をするか裁判で争うかのいずれかにて対応することができます。申立書を作成することができますが、被相続人や相続人すべての戸籍謄本や遺言状の写しや不動産登記事項証明書などといった書類が必要となります。
不動産売買や相続、賃貸管理に関するご相談などございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にご連絡ください。