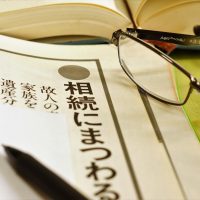障害を持つ方は一般的に経済力に厳しい状況であり、親族の援助などに頼らざるを得ないケースが多くあります。
そこで相続の制度では相続人に障害を持つ人がいる場合には障害の程度に合わせて税額から所定の金額を控除できる障害者控除というものがあります。
障害者控除の制度
障害者控除は相続税の税額から直接控除できる制度であるため大きな税の軽減効果を受けることができます。障害者控除は相続人であれば誰でも適用できるというものではなく、次の要件をすべて満たす必要があります。
1 相続財産を取得したとき、日本国内に住所があること
2 相続で財産を取得したときに障害者であること
3 相続で財産を取得した人が法定相続人であること
です。したがって法定相続人ではない人、海外に住所がある人などは障害者控除の適用を受けることができません。また、障害者には一般障害者と特別障害者の2種類があり障害者控除の額が変わります。一般障害者は身体障害者手帳における等級が3~6級、精神障害者福祉手帳における障害等級が2又は3級の人などが該当します。
特別障害者は身体障害者手帳における等級が1又は2級、精神障害者手帳における障害等級が1級の人などが該当します。
障害者控除の控除額
障害が重いほうが障害者控除の控除額は大きくなります。控除額の計算では相続人の年齢が満85歳になるまでの期間で計算を行います。相続したときの年齢が30歳であれば85歳になるまでの55年間について1年間あたりの金額を乗じて障害者控除額を求めます。
この1年間あたりの金額が一般障害者だと10万円、特別障害者だと20万円となります。したがって85歳になるまでの期間が55年間であれば一般障害者では550万円、特別障害者では1100万円の控除額ということになります。
このときの計算で年齢が30歳と10カ月という場合では端数を処理して30歳で計算をするため「85歳-30歳=55歳」となり、納税者に有利な計算ができるように定められています。
控除しきれない場合
上記のように障害者控除が適用できる相続人が若い場合には控除できる金額が大きくなるため相続税額から控除しきれないという事が起こります。この場合には控除しきれなかった金額を他の相続人の相続税の金額から控除することが認められています。
ただし、控除することができるのは家庭裁判所が扶養義務を負わせた相続人の税額からとなりますので注意しましょう。単なる相続人というだけでは控除することはできません。
このように相続における障害者控除は税の軽減効果が大きいので適用できる場合には相続税の申告の際には忘れずに適用するようにしましょう。