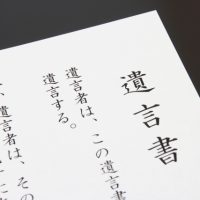相続が発生すると被相続人の財産を相続人が相続することになります。このとき現金や有価証券などであれば良いのですが、賃貸用不動産などを相続した場合には減価償却の方法が問題になってきます。
減価償却とは
減価償却とは長期的に効用を発揮する資産について、その取得に要した費用をまとめて一度に計上するのではなく、効用を発揮する期間に渡って費用化していくことをいいます。不動産のなかで建物や設備などが減価償却資産に該当し、耐用年数に応じて費用配分します。
耐用年数と取得費用、そして減価償却の方法で減価償却費が決まります。減価償却の方法には定額法と定率法があり、定額法は減価償却資産の減価償却費が毎年一定額となり、定率法は一定の割合で償却を行っていくため償却額は年々少額になっていくという特徴があります。
一般の相続では減価償却が問題になることはあまり無いのですが、被相続人の遺産のなかに賃貸用不動産などがあると減価償却が問題となることがあります。
相続における減価償却
現在の税法では建物や設備の償却方法に定率法を採用することはできず、定額法を採用することが定められています。
しかし、相続財産に減価償却を行う賃貸用不動産などが含まれており、被相続人が償却の方法として定率法を採用していた場合、相続人はそれを引き継いで定率法を採用することができます。
しかし、このためには税務署に届出をする必要があり、何も手続きをしない場合には定額法に切り替える必要があります。これを知らないまま定率法を採用していた場合には、後日修正申告を行わなければいけなくなる事がありますので注意が必要です。
一年が13ヶ月に
相続において減価償却資産を引き継ぐ場合に1年が13ヶ月となります。何を意味しているかというと、相続を行った年の減価償却における被相続人の償却月数と相続人の償却月数の合計が13ヶ月になるということです。
これは相続における償却月数の計算が1ヶ月未満の端数を切り上げて計算することに起因します。例えば被相続人が6月12日に亡くなったケースで考えてみますと、被相続人の準確定申告で行う減価償却の月数は1月1日から6月12日で12日は切り上げるために6ヶ月として計算を行い、相続人の減価償却は6月12日から12月31日までで切り上げを行うため7ヶ月となります。
6ヶ月と7ヶ月の減価償却を1年間で行うこととなり、合計月数が13ヶ月となるのです。何となく違和感を覚えるかもしれませんが、税法で定められており間違いではありませんのでご安心ください。