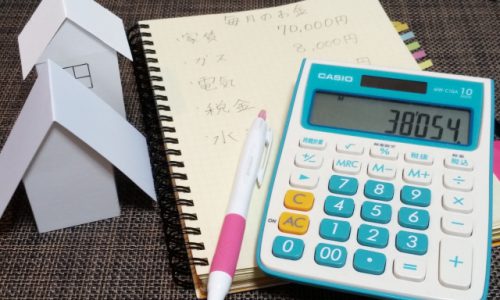歴史的な低金利が続き、資金調達の環境が良好になったことから賃貸用のアパートやマンションを購入して不動産投資を行うのがブームになっています。
不動産投資の目的のひとつは家賃収入から利益を獲得することですから、一義的には利益率が高い物件が大家にとっては良い物件ということになりますが、賃貸経営の内容次第で利益率は影響を受けることに留意しなければいけません。
投資物件の利益率とは
アパートやマンションの賃貸経営における利益とは獲得した家賃収入に対して賃貸経営に必要な全ての費用を控除した手残り額のことです。この手残り額の家賃収入に対する割合を利益率といいます。ちなみに賃貸経営に必要な費用の家賃収入に対する割合は経費率といいます。
不動産投資を始めるに際して多くの方は不動産投資ローンなどを利用することになりますが、手残り額からローンの返済を行いますので手元に残る金額は更に少なくなります。しかし、ローンの返済は投資物件の利益率の計算に当たっては考慮しないのが一般的なので注意しましょう。
物件やエリアによって異なる利益率
賃貸用不動産の利益率は物件やエリアによって異なります。獲得できる家賃収入の割に維持費が高額となる物件や空室の発生が高い物件は利益率が低くなる傾向があります。一方で獲得できる家賃が高額になる都心の物件などは利益率が高くなる傾向があります。
もちろん賃貸経営の成否を考えるとアパートやマンションの購入価格も重要な要素ですから、利益率だけで不動産投資の成否が決まる訳ではありません。
賃貸経営と利益率
投資用不動産の利益率には上記で記載した傾向はあるものの絶対的なものではありません。実は賃貸経営の内容次第で改善もすれば悪化もするのです。
例えば利益率が80%近くある優良な物件であっても賃貸経営が良好に行われていなければ運用を続けていくうちに利益率が下がっていくことになります。その反対に利益率が60%程度であっても賃貸経営が良好に行われることで70%に上げることが可能な物件もあります。
賃貸経営の内容
利益率は家賃収入の額と賃貸運用に必要な費用で決まります。家賃収入を上げ、費用を下げることで利益率は改善するということです。家賃収入を増やすためには家賃を上げる又は空室の発生を抑えることです。
賃借人が退去した際にリフォームを行い、賃貸需要を高めることで家賃を上げたり、空室期間を短くしたりすることができるケースがあります。費用については管理業者の見直しなどを行うことで管理水準は下げずに費用を抑えることができるケースがあります。
このように賃貸業を経営するという観点で大家が手を入れていくことで利益率が改善することは十分にあります。一方で何もしなければ空室が長引き、家賃を下げて募集することになり利益率は悪化することになってしまいます。
不動産投資では経営の視点をもって運営していくことが大切なのです。