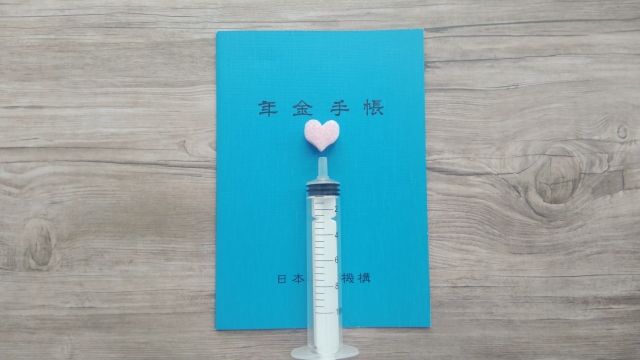専業主婦のような片方の収入で生計を立てていた夫婦が離婚後、配偶者側は老齢基礎年金しかもらうことができず、苦しい生活を強いられることになります。しかし、特定の条件に当てはまれば婚姻期間中の厚生年金記録を分割することが可能です。
合意分割制度とは
平成19年以後に離婚し、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、当事者双方の合意または裁判手続きにより、按分割合(対象期間、当事者同士の標準報酬額に対して分割後の分割を受ける側の持ち分を表したもの)を定めることで分割することができます。
分割請求の期限は離婚が発生した日から2年以内で、分割した後に標準報酬月額・標準賞与額に基づいた老齢厚生年金を受けるには、厚生年金の加入期間・国民年金保険料が受給可能期間を達成、支給開始年齢に達していることが条件に含まれます。
双方の合意がある場合と話し合いで解決しない場合
双方の協議で合意した場合は、証拠として「公正証書」「認証を受けた私署証書」にその旨を記載しなければなりません。話し合いで決まらない場合は、どちらか一方が家庭裁判所に申し立てすることで第三者を交えて按分割合を決めることができます。
厚生年金を合意分割した側とされた側の計算方法
厚生年金記録を分割した側において、分割した本人の厚生年金記録から、分割した標準報酬月額・標準賞与額を差し引いた額から年金額を計算します。
分割を受けた側は、本人の厚生年金記録に相手から分割された標準報酬から年金額が計算されます。
3号分割とは?
3号分割とは夫婦の合意なしで年金分割できる制度です。3号は国民年金の第3号被保険者のことで、国民年金被保険者は
第1号被保険者:自分で国民年金保険料を支払っている被保険者
第2号被保険者:厚生年金に加入している人
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者
というように分類されています。条件はかなり限定されており、「平成20年4月1日以降」「婚姻期間に第3号だった期間がある」「年金分割の請求時効である2年を経過していない」「相手が障害厚生(共済)年金の受給権者ではない」の4つをクリアしなければなりません。
3号分割は標準総額に関わらず半分に分割できるため、年金が少ない側がさらに分割される危険があります。もし不公平な内容の「第三号被保険者期間に係る年金分割のお知らせの通知」が届いたら、合意分割の申請を行いましょう。
まとめ
按分割合を決めるための標準報酬額・標準賞与額・分割できる期間を調べる必要があり、年金事務所に情報提供の請求を行うことで取り寄せられます。請求は合意分割の請求期限内に行わなければなりませんので、その後の話し合いを十分に行うために、離婚後できる限り速やかに請求するようにしましょう。後々トラブルに発展しないように、当事者同士でしっかり話し合い、お互いに納得のいく合意分割を行ってください。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。