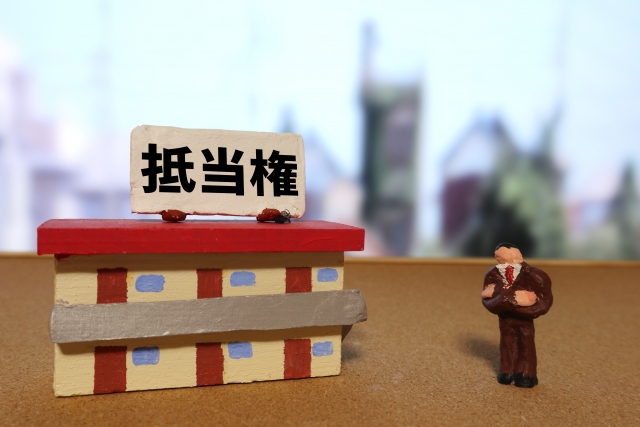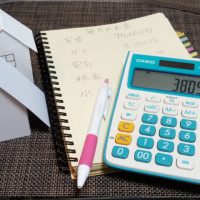住宅ローンを借りる際、金融機関が「抵当権」というものを設定することがあります。これは万が一返済が滞った場合を考えて土地や建物にかける「担保」のようなものです。今回はローンを組む人には欠かせない抵当権の知識について解説いたします。
抵当権とは?
金融機関で住宅ローンを組むとき、債権者である銀行が借主、つまり債務者に対して設定することのできる権利です。貸す方としては、ローンの返済が滞ってしまっては困ります。ですから、土地や建物を万が一の保険とも言うべき、「担保」とするのです。これが「抵当権」になります。
万が一ローンの返済が滞った場合、銀行は抵当権を行使して、債務者の物件を差し押さえ、競売にかけることができます。どの程度の遅滞で差し押さえられるかはケースにもよりますが、督促状が届いたら注意が必要です。
抵当権は抹消できる
住宅ローンを完済してしまえば、抵当権は抹消することが可能です。ただ、完済後に金融機関が勝手にやってくれる訳ではありません。銀行はあくまでもお金を貸しているだけなので、抹消するためには自分で手続をする必要があるのです。
もし、完済後も抵当権を抹消しないままでいると、不動産登記の上では設定されたままの状態になっているので、該当する住宅を売却するときなどに、トラブルが発生する可能性があるのです。
抵当権抹消のやり方
ローン完済時に銀行から必要な書類が送られてくるので、法務局に足を運んで手続するか、司法書士に代行してもらいましょう。登録免許税という手数料がかかり、司法書士に相談する場合は依頼料もかかります。
また、ローンを返済中でも抵当権を抹消することは可能です。そのためには住宅を売却し、買い手から売買した代金を払ってもらって、それを残債に当てる形になります。このとき、売却金額が残債を下回る事の無い様、見積もりには十分に注意しましょう。
抵当権つきの物件を相続することもできる
抵当権が設定されている物件でも相続の対象となるので、通常の不動産と同様、相続税がかかります。設定のあるなしに関わらず、不動産の評価額に影響はありません。ただし、所有者に借金がある場合、財産からの差し引きで相続税が算出されます。
たとえば、親の財産が住宅のみであり、多額の住宅ローンが残っている場合などは、相続を放棄するという手段も考える必要があります。ただ、住宅ローンを組む際に団体信用生命保険、通称「団信」に加入しているケースでは、住宅ローンの名義人に万が一の事があったときは保険金が支払われて残債を完済できます。
まとめ
今回は住宅ローンと抵当権についてお伝えしました。人生に関わる事柄ですので、設定されている物件に住んでいる場合は、ローンの返済計画には十分に留意しましょう。また、万が一のときに備え、対応するための手段を用意しておくことを怠らないようにしましょう。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。