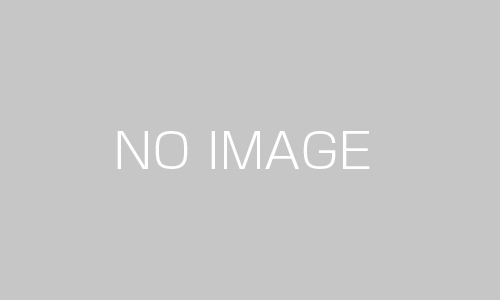相続が発生すると、どこまでの親族が相続人になるのかということが問題になることが良くあります。実はこの問題と同じくらいに重要なのが、どこまでの範囲が納税義務の対象となる財産なのかということです。
実は相続税は生前に贈与したものも対象になります。この問題について確認してみましょう。
相続税の仕組み
国税庁のホームページによると、「相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。」とあります。
相続税というと、被相続人が死亡したときに所有していた財産が課税範囲のように思われますが、上記のように被相続人が死亡する3年前まで遡って行われた贈与財産は相続税の納税義務の対象となるのです。
生前贈与とは何か
生前贈与とは、生きている間に財産を譲ることを指します。贈与となりますので贈与税が発生するのですが、毎年1月1日から12月31日までの間に1人当たり110万円までは非課税となるために、納税義務が発生せず相続税の節税のテクニックとして広く知られています。
110万円を超える贈与を行った場合には、超過した金額に贈与税の納税義務が発生しますが、相続財産が高額な方の場合には贈与税のほうがトータルでは安く済むケースがあります。例えば贈与の対象となる金額が200万円の場合の税率は10%ですが、相続財産の金額によっては10%を優に超える税率が課税されることがあるためです。このため生前贈与を上手く使って相続税の納税義務の対象となる財産を減らしていくのです。
3年以内のルール適用の範囲
この3年以内のルールの設定は相続税の納税義務の回避を目的として、死亡する直前に駆け込みで生前贈与が行われることを防ぐためのものです。このため死亡するまでの3年以内の生前贈与の全てが無効になる訳ではなく、相続人に対して行われた生前贈与が対象となります。したがって被相続人からみて孫や子供の配偶者などに対して行った生前贈与は相続税の納税義務の対象とはなりません。
しかし、遺言によって配偶者や孫が相続人になる場合や、孫が代襲相続人となるような場合には3年以内の生前贈与の金額が相続税の納税義務の対象となりますので注意が必要です。なお、生前贈与が相続税の納税義務の対象財産となった場合には既に納税した贈与税がある場合には、相続税の金額から控除する事となります。
相続税、贈与税の仕組みは複雑ですので、生前贈与を利用して節税を行う場合には相続税に詳しい税理士へ相談しながら行うことをお薦めします。