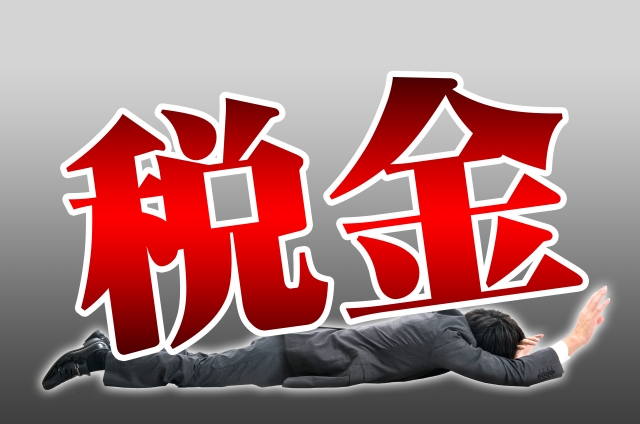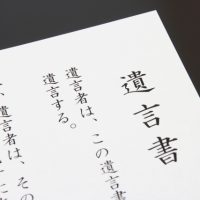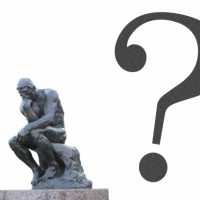相続になっている家に住んでいると税金はどうなるのでしょうか。租税の割り当てや取り立てに関する法律である税法の改正により、相続税の課税対象になる相続が近年増えてきています。
■住宅の相続税による申告
住宅などの不動産を相続する場合、3000万円+相続人の数×600万円基礎控除額を超えると相続税が課税されるため、節税対策を考える必要があります。
方法としては土地の評価額を下げてくれる80%~50%まで評価額を減らしてくれる「小規模宅地の特例」や、配偶者控除に加えて生前贈与における贈与税の非課税制度である「住宅取得資金贈与の特例」があります。住宅や土地などの不動産を相続した時に発生する相続税の算定基礎について確認していきましょう。
■基礎控除額を越えていない場合はかからない
住宅の相続税に関しては、不動産か預金、貯金に生命保険の財産などの税金がかかる対象となりますが、下記のような場合はかかりません。
・相続遺産の合計額-基礎控除額(3000万円+相続人の数×600万円)=課税遺産総額
相続人の数が多いほど基礎控除額が増えていくことが分かります。プラスの相続遺産から借金や葬儀代を引いた額(相続遺産の合計金額)が基礎控除額よりも少なければ、相続税は1円もかかりません。
■二世帯住宅は少し例外がある
被相続人の配偶者が取得した土地ではなくても親族が住んでいる宅地は小規模宅地の特例が二世帯住宅でも適用されます。
ところが、普通住宅の二世帯住宅であっても、住宅内で行ったり来たりできない造りになっていて別々で登録をする区分所有登記小規模宅地の特例にはならない時もあるので気を付けましょう。
■相続税の申し込みは10ヵ月
今まで住宅の相続についてお話をしていきましたが、相続税の申し込みがないと減税の対象にはなりません。もし、10ヵ月以内に間に合わない時は「申告期限後3年以内の分割見込み所」という書類を提出しなければなりません。10ヵ月とは、被相続人が亡くなった次の日から数えての10ヵ月です。
■まとめ
今回は、住宅に対する相続の税金における減税の特例をうまく活用できれば、節税にもつながります。状況によって活用できないときや活用しても後で損が出てくる場合もありますので、自分で判断できない時は税理士などに相談してみましょう。
また、小規模宅地の特例や二世帯住宅について詳しいことが知りたい方は、別の記事にありますので株式会社アブローズまでご連絡頂けると幸いです。