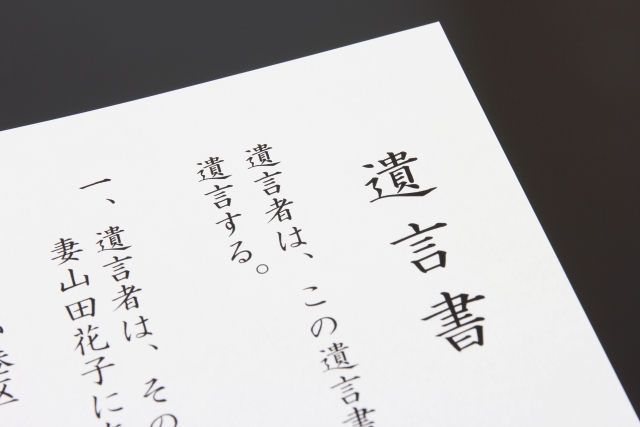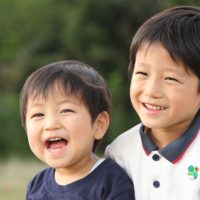日本人は、誰しも財産があろうとなかろうと相続の問題を経験することでしょう。あなたが知らないだけで名義変更のなされてない相続対象の不動産があったりもします。そんな時に相続税の支払いに困らないように、相続税の控除や特例について紹介していきましょう。
■相続の時に使える基礎控除とは
財産を相続した場合には、すべての相続人に対して利用できる「基礎控除」については、相続した財産の時価の総額から「基礎控除」の額を超えなければ「非課税」となって相続税の支払いは免除されます。「基礎控除」の額を超えた場合には相続税の支払いを行うことになります。相続する額によっては大きな支払いが一度に必要となる為、相続税の知識は必要とされその後の対応に役立てる事ができます。
◎基礎控除の計算とは
3000万 + (相続人の人数 × 600万)
■相続税の控除ができる場合とは
財産の相続する対象者によっては、控除を受けることが出来ます。
◎配偶者は大幅な減額の控除が与えられている
被相続人と共に配偶者は財産を作り上げたとみなされて、その後の生活を保障する事を目的に配偶者控除によって相続税の優遇がなされています。以下のA又はBを選びます。
・A配偶者の課税価格(配偶者が相続する財産)が1億6千万円以内までは相続税がかからない。
・B課税価格(配偶者が相続する財産)が1億6千万円を超えても法定相続分までなら相続税はかからない。
※配偶者の法定相続分とは「1/2」「2/3」「3/4」と対象によって割合が変わります。
◎未成年に対する控除とは
相続人が20歳になるまでは年度毎に10万円の控除ができます。
◎障害者に対する控除とは
障害者が相続の対象になる場合には85歳まで年度毎に10万円の控除ができます。
特別障害者に関しては85歳まで年度毎に20万円の控除ができます。
◎相次相続控除の場合は
10年以内に父や母が相次いで亡くなった場合には2回以上の相続のうち1回目の支払った相続税から一部が控除されます。
◎暦年課税の贈与税額の控除
3年以内の贈与税の支払い分に対して二重の課税を避ける為に控除の対象となります。
◎外国で支払った相続税の場合
外国での課税額または、相続税の額×(海外の財産の額÷相続人の相続財産の額)
※どちらか少ない方を控除できます。
◎生前にできる相続税の節税対策(生前贈与税の控除)
相続時精算課税制度では、20歳以上の子や孫に生前贈与を行い相続した時に贈与税を控除する制度で、相続税と贈与税を相続時に精算する事になります。
※2500万円まで非課税で贈与できることになります。相続税の先送りと捉えた方が良い。
◎暦年課税は相続財産を減らす事で節税につながる
暦年課税は年間に110万円以内なら非課税で年度毎に贈与が出来て相続財産を減らし節税が期待できる。
※相続時精算課税制度を使った場合には利用できない。
◎小規模宅地等の特例を受けるには
土地の評価額を最大で80%から50%までの減額ができます。被相続人”又は“被相続人と同じ財布で生活していた親族の宅地や借地権の対象。
①特定居住用宅地等の条件=限度面積は330㎡で減額割合は80%
②特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等=限度面積は400㎡で減額割合は80%
③貸付事業用宅地等=限度面積は22日00㎡で減額割合は50%
※要件に関しては細かい条件を全てクリアしなければならない。不動産業者や税理士の指導を受ける必要があります。
相続に関する基礎控除やその他の控除について解説しましたが、個人でも相続税の対処はできますが、相続問題に関しては対応がトラブルのもとになりかねません。無料の弁護士相談や場合によっては正式に弁護士を雇う事も必要でしょう。
不動産の賃貸管理や不動産の投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。