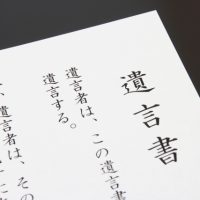”相続”が発生した際、納税義務者となるのは、相続(又は遺贈)により、財産を取得した個人ですが、これは法律上何種類にも分けられています。今回は、相続と納税義務者について詳しくお話していきます。
■納税義務者の種類は4つある。
◎居住無制限納税義務者
相続発生時、相続人が日本国内に居住している場合、日本人、外国人を問わず該当します。
相続した日本国内にある財産、国外にある財産を問わず、全ての財産に、相続税が課されます。
◎非居住無制限納税義務者
日本国内に住所を有さない場合、相続した財産のうち日本国内にある財産には相続税が課されます。但し、下記1と2に該当する場合は、相続した財産の全てに対し、相続税が課せられます。
1:日本国籍を有する個人。(相続発生の開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合のみ該当)
2:相続発生時に、日本国籍を有しない個人が、相続発生時に日本国内に住所を有していた場合に限る。
◎制限納税義務者
相続発生時に相続人が日本国内に住所を有さない者。
1:相続人が日本国籍を有するが、相続、及び被相続人が5年以上日本国内に住所を有していない場合。
2:相続人が日本国籍を有しないが、被相続人が相続発生時に日本国内に住所を有していなかった場合。
上記の条件それぞれに対し、日本国内の相続財産に対して、相続税が課せられます。
◎特定納税義務者
”相続”をしなかった者で、相続時精算課税の適用を受ける財産を”贈与”により取得していた場合、相続時精算課税の適用を受けた財産に相続税が課せられます。
■相続時精算課税とは
相続時精算課税とは贈与税を減額することができる制度です。贈与額の総額から2,500万円まで非課税になります。但し、それを超えた分は20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税を求める式は下記です。
(課税価格-特別控除額)× 税率=納付税額
◎生前贈与との相違点
相続税をできるだけ節約するための制度に、”生前贈与”があります。これには、受贈者一人当たり、年間110万円を超えると、10%から55%の贈与税がかかってしまうという特徴があります。
贈与税の課税を避けようとすると、毎年110万円までしか贈与できないため、時間が長くかかるという欠点があります。短期間に多くの財産を贈与するためには、相続時精算課税制度を利用すると良いでしょう。
◎相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度は、被相続人の生前に贈与した財産を、相続時に再計算する制度です。実は、贈与された財産にも課税される制度です。つまり、節税効果は期待できますが、相続税がなくなるわけではないということです。
■まとめ
今回は『相続発生!納税義務者は誰になる?』と題して、お送りしてきました。
相続と納税義務者、そして相続時精算課税制度について理解が深まれば幸いです。
不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。