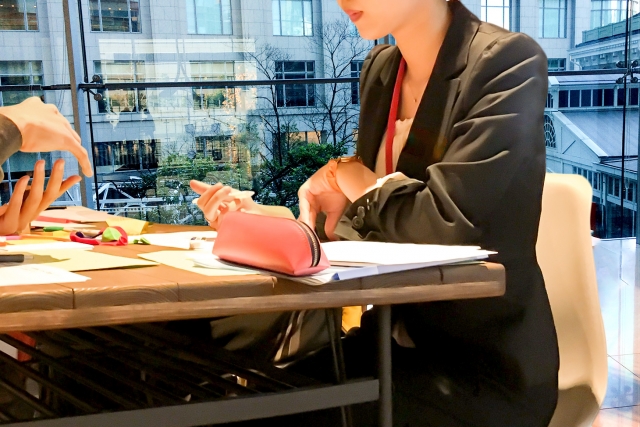婚姻関係にある相手のことを配偶者といいますが、相続が発生したとき、民法の定めでは配偶者は常に相続人となります。
したがって夫が亡くなれば妻、妻が亡くなれば夫は特別なことが無い限りにおいて必ず相続人となるということです。では、妻が相続人となる場合に気を付けるべきポイントには何があるでしょうか。

婚姻関係が必要
相続において争いになることもあるのですが、配偶者とは婚姻関係にある者のことをいいます。したがって過去に婚姻関係にあったが今は離婚している者、婚姻関係の無い内縁の妻は配偶者には該当しません。
また、離婚した妻が婚姻時に出産した子供は当然に、内縁の妻が出産した子供も認知や養子とすることで相続人となりますが、子供を出産したとしても婚姻関係になければ子供の母親は相続人にはなりませんので注意が必要です。
妻が受け取れる相続分
夫が死亡する前に遺言書などがあれば相続はその遺言書に沿って行われますが、常に遺書が存在するものではないため、民法では法定相続分を定めています。
遺書が無ければ、法定相続分を各々の相続人が受け取ることになりますが、遺産分割協議といって遺産の分割方法について全相続人が合意をすれば法定相続分と異なる相続を行うことも認められています。
夫が死亡した場合に妻が受け取れる法定相続分は、妻以外の相続人が誰なのかによって異なります。妻以外の法定相続人は、被相続人である夫から見て、子供が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。順位が高い相続人が存する場合には、低順位のものは相続人になることができません。
つまり、子供がいれば親や兄弟姉妹は相続人になることはありませんし、子供がいなくても親がいれば兄弟姉妹が相続人になることはありません。
妻以外に相続人がいなければ全ての財産が、妻以外の相続人が子供の場合には遺産の2分の1、親の場合には3分2、兄弟姉妹の場合には4分の3が妻の財産になります。
遺留分について
一般的に妻は夫の資産形成に貢献をしてきたものと考えられるため、もし、遺書などによって最低限受けるべき相続分まで侵害された場合には、遺留分を請求することが認められています。この遺留分については請求する権利が認められているというものであり、黙っていても自動的に認められるものではありません。
また、請求期限があるので十分に注意が必要です。法定相続人が妻のみの場合は全相続遺産の2分の1、子供との場合には4分の1、親との場合には3分の1、兄弟姉妹との場合には2分の1が遺留分として請求する権利が認められています。